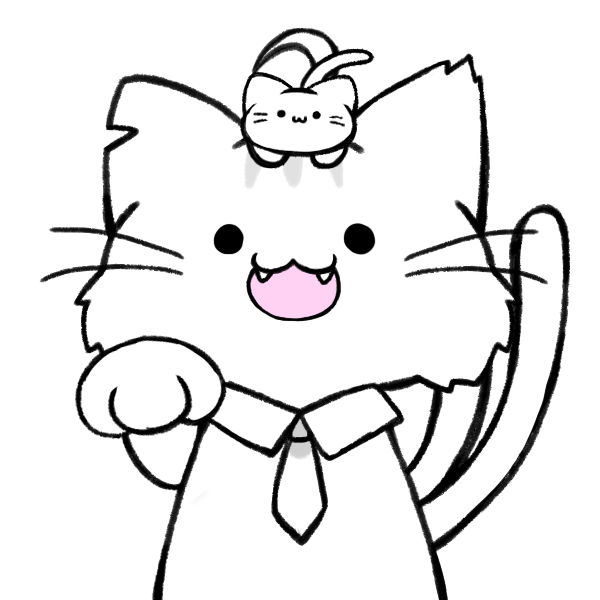「子育て×仕事×勉強」どうやって時間を作った?30代社会人のスキマ時間勉強術
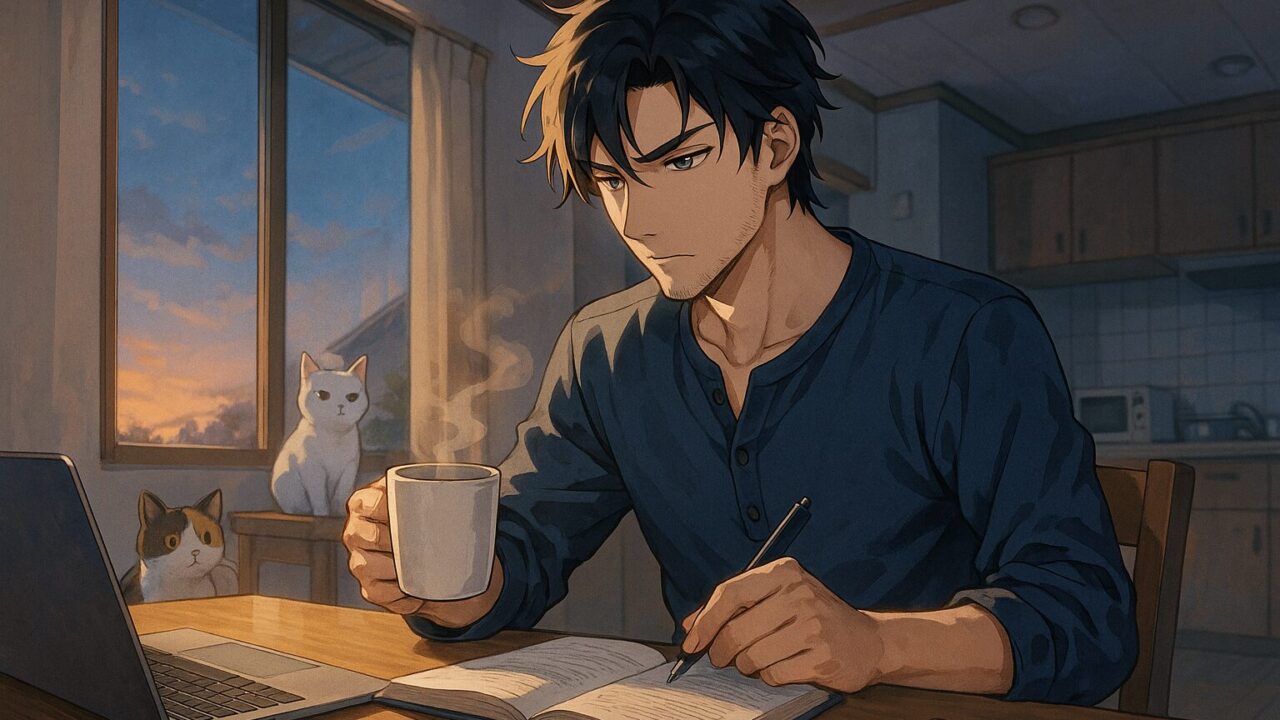
こんにちは、シロです。
「勉強を始めたい」と思っているけど、実際に行動できない人は多いのではないでしょうか。
「仕事が落ち着いたら、子どもが大きくなったら、きっとできるようになる。」
そう思っている人も少なくないと思います。
私の場合は、夜はヘトヘトで「もう何もしたくない」と思うことがほとんど。スマホをダラダラ見て、気づけば眠ってしまう日ばかりでした。
また、子どもがいると自分の都合で時間を調整することが難しいです。例えば、保育園や習いごとへの送迎、起床・就寝の時間も大体決まっています。
そんな私のように子育てと仕事に追われながらも、でも無理なく学び続けることができている「現実的な勉強時間のつくり方」と「続けるコツ」を実体験ベースでお伝えします。
誰でも1日は24時間しかないから時間は効率よく使いたいよね
① 1日のスケジュールに「まとまった勉強時間」はない
子育てと仕事の両立をしながら勉強をしようとすると、「夜に1時間まとめて勉強する」といった理想的なスタイルはなかなか実現できません。
私の平日の1日はざっくりこんな感じです。
- 朝:ランニング後に短時間の勉強(30分未満)
- 日中:仕事(昼休みは勉強しない)
- 夕方〜夜:帰宅後、夕食・入浴・寝かしつけ(21:30には一緒に就寝)
- 試験直前:子どもを寝かしつけた後に起きて勉強
私は21時半には子どもと一緒に寝る日がほとんどで、勉強は朝か夜に少しだけ。昼休みは「やらない」ことにしています。雑音の影響で勉強の効率が悪いと感じたため、それなら昼は体と頭を休める時間と割り切るようにしています。
また、朝は体と頭をリフレッシュするために軽くランニングをしています。走った後、子どもたちが起きるまでの時間はわずかに10〜30分しかありません。そのわずかな時間を勉強に当てるようにしています。
ただ、試験直前はどうしても量が必要になるので、寝かしつけが終わったら、勉強時間を確保するようにしています。
こんな生活の中で、「落ち着いてから」「まとまった時間ができたら」なんて言っていたら、きっと一生やらないままだったと思います。
だから私は、「10分でも、15分でもやる」を積み重ねていくスタイルにしています。
まとまった時間で勉強をする必要はなくて、続けられる生活スタイルを作ることが大事。
② 私の勉強法とスキマ時間の使い方
▼基本の流れはこの3ステップ
- 参考書を読む:朝に読むことが多いです。マーカーを引く程度で、書き込みはほとんどしません。一字一句読んでも頭に残らないので、「ですます」部分は飛ばし、太字の前後を中心に読んで理解を深めています。
- YouTubeの解説動画を視聴:参考書で理解できない部分だけ観ます。横になりながら視聴できるのは魅力ですが、記憶の定着率は低いと実感しています。疲れているときの補助的な手段として活用しています。私の場合、簿記の連結会計など、図で見た方が理解しやすい部分を活用しました。
- 過去問を解く:主に夜に紙ベースの過去問を解きます。手を動かすことで眠気がまぎれ、記憶にも残りやすいです。
▼スキマ時間の具体的な使い方
「勉強のために時間を作る」というよりも、「すでにある時間の中から、ちょっとだけ勉強に回す」感覚が近いです。
- 朝の20分:コーヒーを飲みながら参考書を1〜2ページを目安に読む
- 夜の15分:子どもが寝た後、過去問を1問だけ解く
- 職場に早く着いた日の車内:始業時間まで車内で参考書を読む
- 子どもの習いごとの待ち時間:車やコンビニなどで参考書を開く
短時間でも意味があるのか?と思う人もいるかもしれません。私自身は、短時間でもやったことには意味があると感じています。たとえば、朝に読んだ参考書の内容を、子どもの支度やご飯の準備をしながら思い返すことで、記憶の定着がしやすくなると感じます。逆に長時間の勉強では、やった範囲が広すぎて内容を思い出しきれないこともあります。
▼集中できる場所を探す
日中、自宅で集中できる空間がなかなか確保できなかったので、短時間でもひとりになれる静かな場所を自然と探すようにしました。
車もそのひとつです。通勤に車を使っているため、早く着いた日などはエンジンを切った車内がちょうどいい学習スペースになります。
とはいえ、やっぱり一番集中できるのは「子どもが寝たあと」。一日の家事が終わって、ようやくできた自分だけの時間。
一度、寝かしつけで横になってから起きるのはストレスなのですが、「コーヒーを飲むため」などささいな楽しみを見つけるようにしました。
あとは「気合」で起きるようにしています。
ちょっとした楽しみを「やる気」につなげていくにゃ
③ 「とりあえずやる」が、やる気を連れてくる
正直、疲れて「今日はもう無理かも…」と思う日も多いです。
でも、私はそういうときこそ 「とりあえずやる」 ことを大切にしています。
たとえば、頭が働いていなくても、机に向かって参考書を開く。動画を1本だけ観てみる。たったそれだけでも良い。
すると不思議なことに、手を動かしているうちにやる気が出てきます。
「やる気が出たらやる」ではなく、「やったからやる気が出た」。
この逆転の発想こそが、忙しい中で勉強を続ける一番のコツだったと感じています。
もちろん、「とりあえずやる」ことがすべてうまくいくわけではありません。
私自身、今日はもう無理かも…と思いながらも机に向かい、参考書を開いたことがあります。でも数分で「これは覚えられない」「まったく頭に入ってこない」と感じた日は、そこでスパッと諦めます。
疲れたら無理なく休むことも大事だよね!
一度やってみて、それでもダメなら「今日はやらない」と決める。
それくらいの柔軟さも、長く続けるためには大切だと思っています。
④ 完璧じゃなくていい。続けることが一番の成果
時間がなくても、疲れていても、子育て中でも、自分なりのペースで前に進めばいいと思っています。
- 「今日はこれしかできなかった」ではなく、「これだけできた」と考える
- すべて完璧にやろうとしない。「60%でもOK」
- 疲れている日はアウトプット中心。インプットは元気な日に回す
「続けること」自体が、いちばん大きな成果です。
10分でも、1ページでも、動画1本でも。積み重ねれば、ちゃんと前に進んでいる。
私自身、この方法で簿記2級試験に合格できました。スキマ時間の積み重ねでも、成果は出ると実感しています。
⑤ 私が「やらない」と決めていること
- 勉強計画は立てない:計画を立てるのに時間がかかり、守れなかったときにモチベーションが下がる
- 昼休みには勉強しない:雑音が多く集中できないし、仕事中は気持ちが切り替えられない
- スマホやテレビは可能な限り見ない:時間を捻出するには、やめられることを減らす方が確実
- 勉強中に余計なアプリは開かない:YouTubeは参考書で理解できないときだけ。無駄なコンテンツを見るリスクを避ける
特に資格試験は、試験日(=ゴール)が決まっているので、「ちゃんと計画立てないと…」と思うかもしれません。
でも私の場合、細かいスケジュールを立てても、その通りに進められたことはほとんどありませんでした。
そこで、計画を立てるよりも「今日はこれをやる」と決めて動くことにしています。
全体の進捗が気になるときは、月に1回くらい軽く振り返って、「あと何をすればいいか」を確認するだけ。
試験日があるからこそ、無理なく続けられる仕組みのほうが大事だと感じています。
仕事や育児をしていると計画どおりにできないことが多いにゃ
また、「スキマ時間をうまく使おう」と思うなら、逆に”時間をムダにしない習慣”も意識すべきだと感じます。
私にとっては、テレビやスマホを無目的に見る時間がそれでした。
自分のなかで「やめられること」があって、それを見直すことができるなら、一番の時間を捻出になります。
ただ、無理にやめて勉強が続けられないのは本末転倒なので、その時はスキマ時間をうまく活用しましょう。
⑥ まとめ:小さくても、自分の一歩を重ねていく
仕事も育児もある生活のなかで、「勉強時間を確保する」のは簡単ではありません。
でも、「落ち着いてからやろう」と思っていると、たぶん一生そのタイミングは来ません。
まとまった時間がなくても、勉強計画がなくても、勉強が得意じゃなくても、少しずつの積み重ねで前に進むことはできます。
- 朝の10分を活かす
- 夜に15分だけでも過去問を解く
- 「今日は無理」と思っても、まず1回やってみる
特別なことはしていません。ただ、毎日ちょっとだけやる。それだけです。
このブログでは、そんな「勉強は日常の中にある」という感覚を、これからもリアルに伝えていけたらと思っています。
あなたの毎日にも、「少しだけの前進」が増えていきますように。